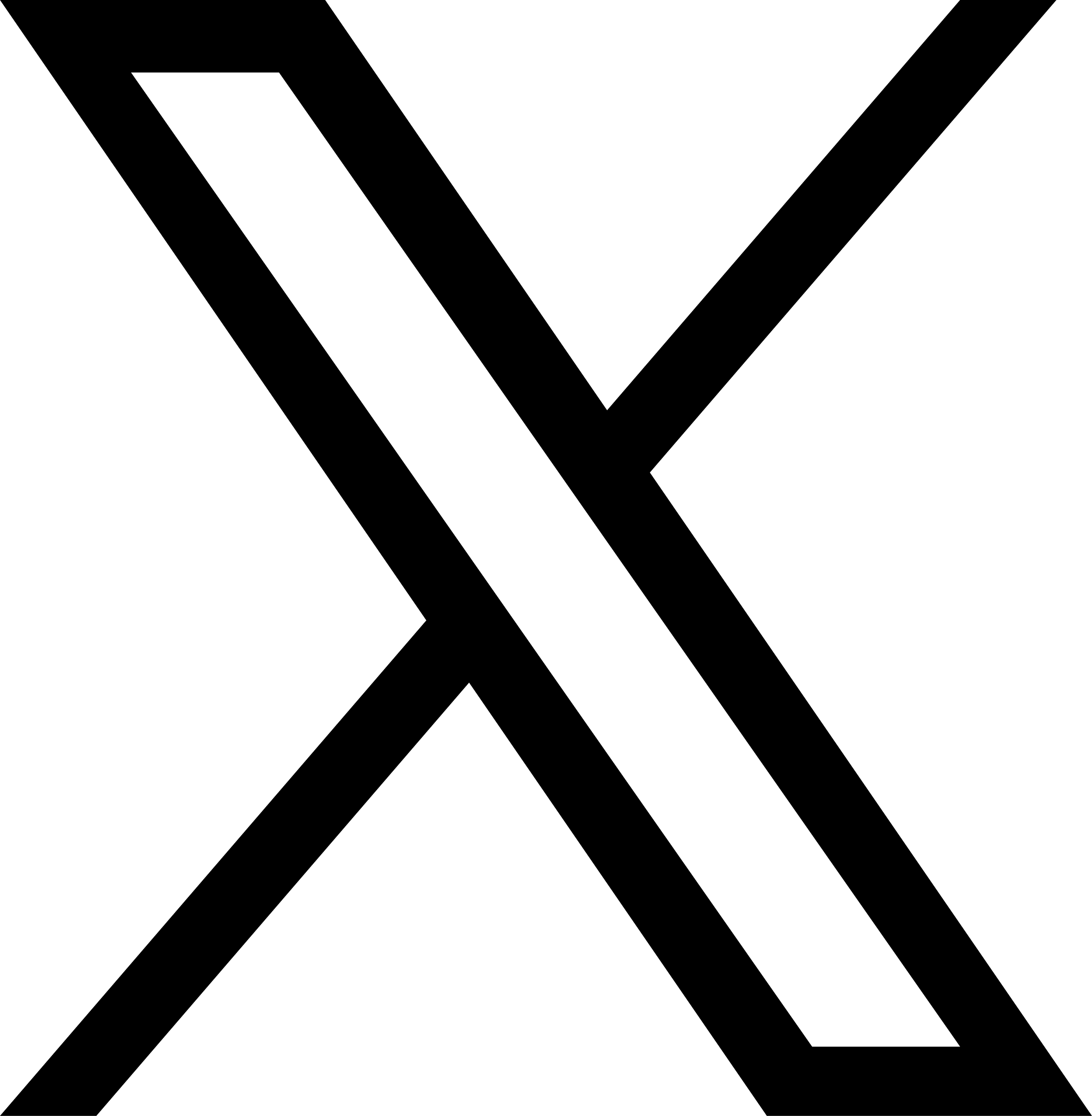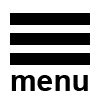コモンズの悲劇と資源管理型漁業
幡谷 雅之(15増大)
元水産庁職員佐藤力生(22増大)は、北洋漁業、資源管理、漁業調整などさまざまな分野(現場)で36年間水産行政に携わってきたが、定年退職を機に三重県下の漁村に移り住み、潮の臭いのする沿岸漁業の現場から、多くの示唆に富んだ情報を発信している。
筆者も水産庁での会議などで、頻繁にお見かけしたことがあるが、豊富な現場体験を通じて得た的確な発言ぶりは、眼光鋭い風貌・容姿とともに今でも記憶に残っている。私の勝手な印象であるが、彼の風貌は、元外交官で作家、日本最強の論客ともいわれる佐藤 優を彷彿させる。
退職後に漁師になる道を選んだ水産庁職員というのは、未だかつて筆者の記憶にない。彼がなぜこのような選択をしたか。それは、資源管理の担当者として、減少した資源を回復させるため、漁業者に休漁を呼びかける会合に出席した際の、ある漁業者の発言からである。「獲りすぎが悪いのはわかっているが、こちらにも生活がある。役人とはわけが違う。そんなこというなら天下りせず漁師になってみろ」。彼は即座に「わかりました。私は天下りしません」と答え、十数年後それを宣言通り実践した。
彼は資源管理型漁業を、日本の漁業が衰退期に陥った時に有効な生き残り戦略と捉え、一般経済への応用を提唱する。我が国経済も今や成長の限界を迎え、「コモンズの悲劇」に陥り始めたようにみえる。
コモンズの悲劇とは、アメリカの生物学者、ギャレット・ハーディンが1968年に『サイエンス』に論文「The Tragedy of the Commons」を発表したことで一般に広く認知されるようになった。
共有地(コモンズ)である牧草地に複数の農民が牛を放牧する。農民は利益の最大化を求めてより多くの牛を放牧する。自身の所有地であれば、牛が牧草を食べ尽くさないように数を調整するが、共有地では、自身が牛を増やさないと他の農民が牛を増やしてしまい、自身の取り分が減ってしまうので、牛を無尽蔵に増やし続ける結果になる。こうして農民が共有地を自由に利用する限り、資源である牧草地は荒れ果て、結果としてすべての農民が被害を受けることになる。
同様に、限りある天然資源に依存する漁業は、個々の漁業者が競って漁獲を続けると、当初は各自の収入は増えるが、ある時点で漁場の生産力を超え、一人あたりの収入は減り始める。行きつく先は漁場の荒廃であり、全員が疲弊し損害を被る。これが漁業における「コモンズの悲劇」であり、これを回避するために、日本各地の沿岸漁業では古くから資源管理型漁業という知恵を編み出し、資源を大切に守ってきた。
資源変動による危機に何度も見舞われてきた我が国漁業の、衰退期の生き残り戦略の智恵を体系化したものが資源管理型漁業である。それは、限られた資源のもと、コストの削減と付加価値の向上を目的とし、地域の漁業者全体の話し合いによる自主的な管理により、最も効率的な操業を目指すものである。資源の衰退期においても一人でも多くの漁業者が生き残っていこうとするものである。
時々の資源状況に応じ、競争と共生を使い分けて、生き残りを図る手法は、日本漁業の伝統である共同体管理ゆえに可能であり、排除の論理で成り立つ競争主義のもとではできないとされている。