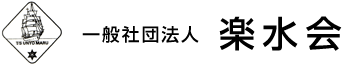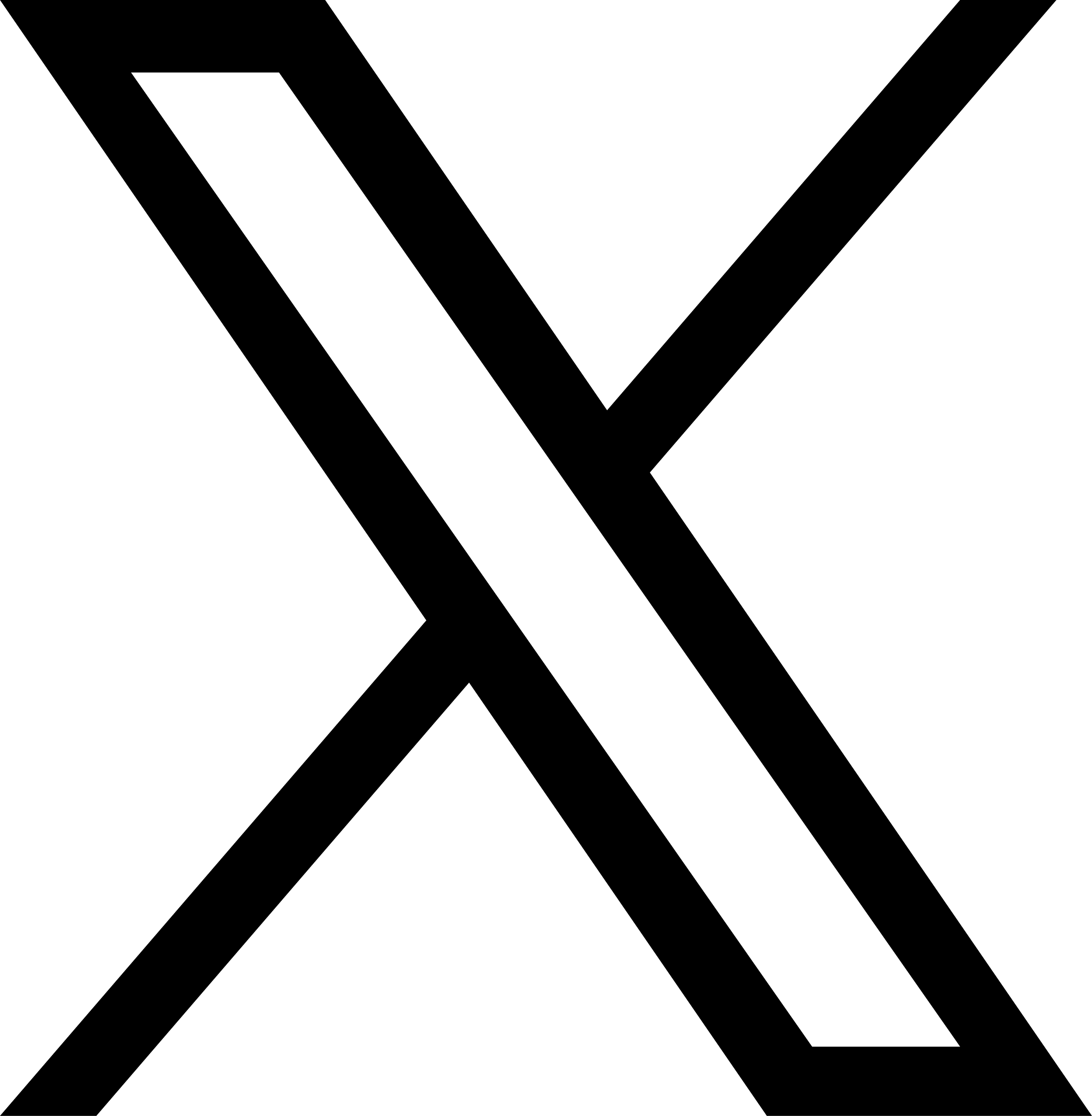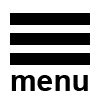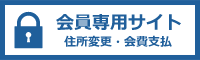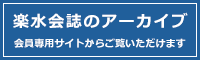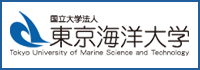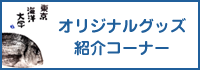タイ王国の楽水会同窓組織について
本澤 雅彦(33漁生)
私は、1991年に東京水産大学水産科学研究科漁場環境学研究室で博士課程を修了し、㈳リモート・センシング技術センターに就職し、地球観測衛星データの利用プロジェクトに従事し、水産以外に農業、林業、環境、災害、気象、都市計画等の各分野における衛星データの調査、研究、実利用分野のプロジェクトを担当しました。
1994年より、タイ王国に駐在し、東南・南アジア地域における活動を展開し、ASEAN 10か国、インド、ネパール、スリランカ等を訪問しました。1997年以降JICA専門家、アジア工科大学院の非常勤教員兼任、JAXAに出向し、定年後の2018年にJICA派遣でチュラロンコン大学、2020年JICA派遣終了後も理学部客員教授、水棲資源研究所客員主席研究員として、研究開発を続け、現在に至っています。
現在関係しているプロジェクトは、①海洋ごみ監視システム、②スマート漁業(養殖、定置網)、③PM2.5監視システム、④減災支援システム(遠地津波、遠地地震)他です。これらは、分野横断型の課題可決プロジェクトのため、産官学の各分野の専門家との共同作業となり、基本的にアイデア提案とプロジェクト管理が主な役割ですが、たまに現場にも行きます。
定年後は、自分ファースト、ゆとりのある研究活動と趣味のスポーツ(ゴルフ、テニス、ボウリング、卓球等)、推し活(乃木坂46)を中心に、タイと日本に拠点を据えて、季節的に行き来しています。日本では、硬式テニス部の同期、高校の同級生が定年後に時間にゆとりが出来ているので、相手をしてもらっています。 最近は、①9月に神宮球場ライブ、②10月に硬式テニス部同期香川ツアー(テニス、観光)等で、親睦を深めています。


写真1 香川県天空の鳥居(2025年10月) 写真2 香川県観音寺テニスコート(2025年10月)
さて、前置きが長くなりましたが、本題に戻ります。海外駐在では、現地での各種コミュニティーへの参加は、日常生活、研究活動をする上で、重要なものです。以下に、タイ王国の楽水会同窓組織について、お話します。
1,タイ楽水会
タイ王国に長期滞在の楽水会会員有志が発起人となり、また楽水会事務局のご指導により、タイ楽水会は、2015年7月に発足を致しました。また、同年7月14日に、田畑 楽水会会長(当時)が来タイされた際に、タイ楽水会幹事との懇親会を開催しました。
タイ楽水会は、楽水会と同様に、大学と同窓会は「車の両輪」を基本理念として、①東京海洋大学とタイの大学:チュラロンコン大学、カセサート大学他、②日本の政府機関(日本大使館、JICA、JETRO、JAXA、NEDO、NICT、JST他)、③国際機間(SEAFDEC、AIT、UNESCAP、UNDP、UNEP、FAO、UNESCO、ADPC、ADB、WB他)、④タイの政府機関(水産局、海洋沿岸資源局、公害局、防災・減災局、気象局他)、⑤日系企業との産官学の連携の支援を行っています。また、会員相互の情報交換、親睦、健康増進、安全・安心な生活に資する活動を行っています。
会員数は、7~8人程度で推移し、LINEグループで情報交換を行い、懇親会、ゴルフ親睦会等を実施し、会員間の親睦を深めています。



左から
写真3 田畑会長(当時)タイ訪問(2015年7月)
写真4 ゴルフ親睦会(2022年10月)
写真5 懇親会(2023年12月)
2,TUMSAT/TUF Alumni
東京水産大学、東京海洋大学のタイ人卒業生中心のコミュニティー、現在70名超の大所帯。LINEグループで、情報交換し、言語は、タイ語、英語、日本語が入り乱れております。主に、情報交換の場でしたが、本年8月末に東京海洋大学主催の懇親会を開催しました。

今後のタイ楽水会の活動として、以下を考えています。
- タイ国内の同窓生の把握、名簿作成、懇親会等の開催
- タイ人同窓生コミュニティーとの交流
- 練習船寄港、交換留学生、海外探検隊への支援
- 東京海洋大学とタイとの研究交流(SATREPS他)、産官学連携
(チュラロンコン大学水棲資源研究所客員主席研究員、タイ楽水会代表幹事)