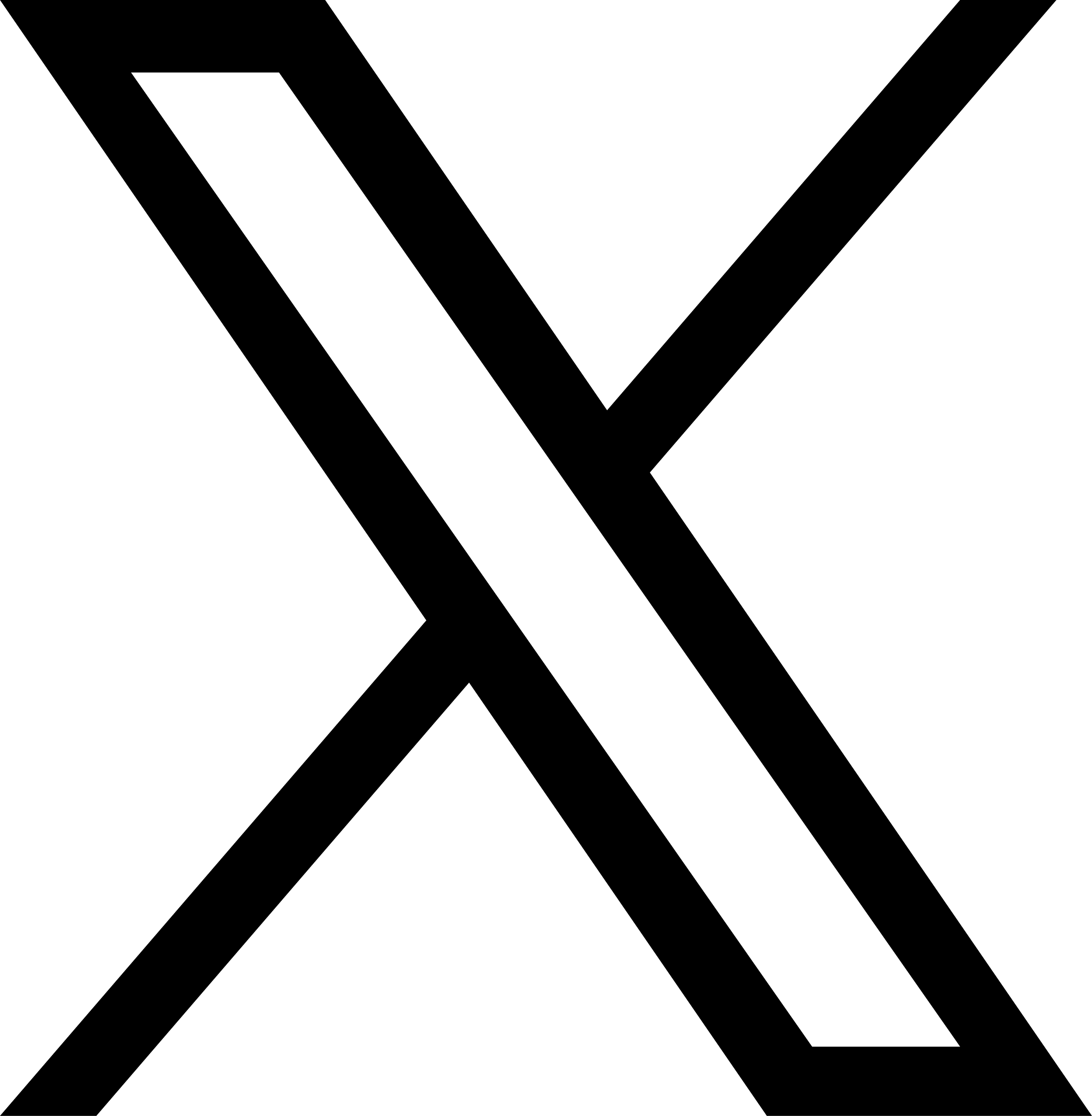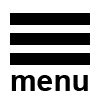ハモの味
幡谷 雅之(15増大)
ウナギ、アナゴ、ハモなどの魚類は無足類と呼ばれ、古くから日本人の食生活にきわめて密接な関わりを持っている。この中で、ウナギとアナゴは、漁獲も消費も全国区の魚だが、ハモは何といっても関西の魚だ。ハモは岩礁の隙間に潜み、カニやタコなどを捕食する。その大きな口と鋭い歯が特徴である。美食家として知られる谷崎潤一郎はハモが好きで、グレーハウンド犬のことを「鱧みたいな犬」と形容した(『蓼食う虫』)。
ハモの旬は6~7月だが、関西では京都の祇園祭や大阪の天神祭でもハモ料理は欠かせない。俳句でも生きものとしてより、食べものとして詠まれることが多い。
鱧食べて夜がまだ浅き橋の上 草間時彦
ぱったりと風とまり鱧のざくざく 宇多喜代子
*「鱧のザクザク」は鱧皮ときゅうりの酢の物
ハモは生命力の強い魚で、海から遠い京都へも生きたまま運んでこられたという。鱧料理は主に関西で発達した。ハモには長くて硬い小骨が非常に多く、食べるには「骨切り」という下処理が必要となる。京料理の板前の腕の見せ所であり「はもの骨切り 手並みの ほどを見届けん」の句がある。「一寸(約3センチ)につき26筋」包丁の刃を入れられるようになれば一人前といわれる。
骨切りの技術が京都へ伝わったことによりハモの消費が飛躍的に増えた。骨切りを施したハモを熱湯に通すと反り返って白い花のように開く。これを「湯引きハモ」または「牡丹ハモ」といい、そのまま梅肉やからし酢味噌を添えて食べるほか、吸い物、土瓶蒸し、寿司、天ぷら、蒲焼や唐揚げなどさまざまな料理に用いられる。 上質なカマボコの原料にも使われる。その際残った皮を湯引きして細かく切ったものは、酢の物にも利用される。
京都では、生活に密着した食材で、鱧の湯引きなどはスーパーでも販売されており、安くはなくとも、季節の食材として扱われている。特に祇園祭の暑い季節に長いものを食べると精力が付くとして、ウナギ同様に食べる風習があり、夏の味覚の代表的なものとして珍重される。家庭で「骨切り」をすることは難しいが、鮮魚店で骨切りをして、生で売られている。京阪以外の地域では、味は良いが骨が多く食べにくい雑魚として扱われ、蒲鉾や天ぷらの材料として使われてきた。特に大阪などの蒲鉾屋では身を使った後のハモの皮が売られていることがある。
一方、関東など東日本では京料理を提供する高級日本料理店以外ではあまりお目にかかることはなく、生活に密着した食材とは言えない。このような店で出される食材のため、高級魚というイメージもある。消費量も関東のハモ消費量は関西の10分の1程度であり、関西と関東の食文化の違いが如実に表れている食材の一つである。
ベストセラー作家の湊かなえは、生まれ育った因島(現広島県尾道市)から、結婚を機に淡路島に移り住んでから、京都の料亭で出される気取った料理という、自らが長い間抱いていたハモのイメージが変わったという。
淡路島では、ハモは夕飯の定番食材であり、夏になれば骨切りをした生のハモがパックに入って、家計に優しいお手頃価格で、肉や野菜と一緒にスーパーの棚に並ぶ。一番の好物はハモと玉ねぎの卵締めである。淡路島といえば玉ねぎ。肉厚でみずみずしく、甘味があり、長時間水にさらさなくても辛くないのが特徴である。ホクホクのハモとトロトロの玉ねぎとフワフワの卵が絡み合い、極上の旨味と食感を堪能することができる。旬を過ぎた秋のハモも脂が乗って味が濃く、ますます卵締めにはもってこいである。
小津安二郎監督の映画『秋刀魚の味』(1962)は川崎市の話だが、恩師の佐久間(東野英治郎)が教え子の宴会に呼ばれ、生まれて初めてハモを食べた。
「美味い 美味い。こんな美味いものは、生まれてこのかた 食ったことがありません。
これはなんというものですかいの?」
教え子の一人が、「先生それはハモです」
すると先生、「ハム?」「いやハムじゃなくハモ」
「アア、ハモ―なるほど結構なもんですなア。ウーム、鱧か…。魚へんにユタカ…」
と納得した様子。
酔いつぶれて畳に臥している先生をみた教え子の一人が
「ヒョータン先生(先生のあだ名)、ハモの字は知っていても、食ったことがねえんだぜ」
と知識だけの教師を皮肉っている。