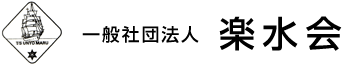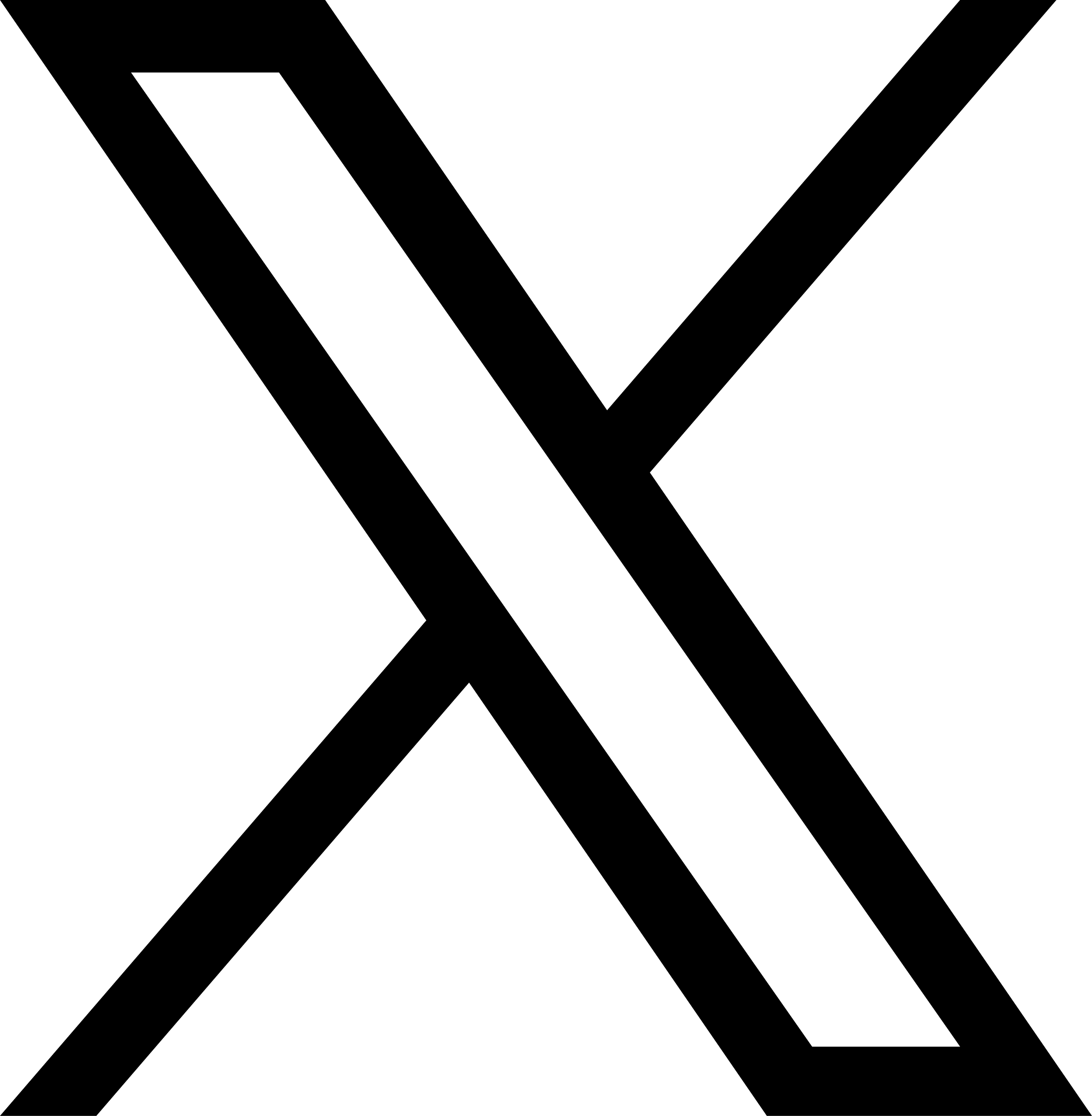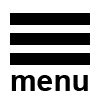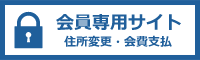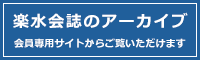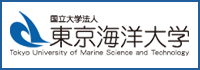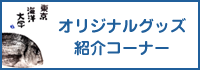新春のご挨拶
東京海洋大学 学長 井関俊夫(特会)

楽水会の皆様、新年明けましておめでとうございます
本学学生をいつも温かくご支援くださり誠にありがとうございます。本年もよろしくお願いいたします。
昨年の9月22日に「さかなクン探究隊」の結成式が白鷹館で行われ、開催協力校を代表して挨拶をしてきました。「探究」という言葉は、平成30年3月の学習指導要領の改訂において「自己の在り方、生き方を考えながら、よりよく課題を発見し解決していくための資質・能力」の育成のため、それまでの「総合的な学習の時間」が「総合的な探究の時間」に変更されたことを契機として、良く耳にするようになりました。さかなクンは令和5年の8月に永岡文部科学大臣から「みんなの探究応援大使」を委嘱され、海洋や漁業分野の研究に関する広報発信や、魚介類系の食文化の魅力発信などを行っています。「さかなクン探究隊」もその活動の一環のようで、小学校4年生から6年生までの11人の児童を隊員として、「お魚と海の未来を考えてみよう」をテーマとする体験ワークショップ、特別授業、発表会などが月1回のペースで計7回実施される予定です。
この企画の目的は、好きなことや興味のあることをとことん「探究」する大切さおもしろさを知ってもらうことで、本学からは清水悦郎教授、内田圭一教授が講師となり、電池推進船と海洋プラスチックについての探求プログラムを提供しています。私は初日の挨拶だけだったのですが、11人の子どもたちのキラキラした目を見ていると、とにかくかわいくて、こちらまで元気になりました。挨拶のなかでは、この11人の隊員全員が東京海洋大学に入学することを期待しつつ、「探求学習」はとてもおもしろくて、答えにたどり着いたときの爽快感は格別であることを強調しました。
大学における「探求学習」の主要なものとしては、やはり卒業研究があげられると思います。卒業研究では先行研究の調査、実験の計画や研究の進め方、解析手法そして論文の書き方などを学び、研究者としての第一歩を踏み出すことになります。教員にとって学生指導は楽ではありませんが、学生たちの積極性が見え始めたときは、教員を続けていてよかったと思えるときでもあります。
一方で、教員が学生の学びをコントロールできるかと言えば、そのようなことはなくて、若者の突飛な発想に逆に刺激を受けることもあります。教育の本質とはそんなところにあるのではないでしょうか。高校における探求学習の本格導入は令和4年からということですので、今年の4月から「探究学習」を経験した学生が入学してくることになります。これまでの学生との違いがあるのかどうか、非常に興味があるところです。
昨年の6月に国立大学協会から「我が国の輝ける未来のために」という緊急声明が出されました。そのなかに書かれている「もう限界です」という言葉が大きく報道されましたので、ご存知の方も多いかと思います。物価高騰や円安の影響で財務状況が悪化している国立大学の状況を理解してもらい、運営費交付金の増額などを求めるための緊急声明です。東京海洋大学においても苦しい状況は全く同じです。「我が国唯一の海洋系大学」としての教育研究を維持発展させるよう努力を続けていきたいと思っています。楽水会の皆様には今後も変わらぬご助言、ご支援をいただけますと幸いです。