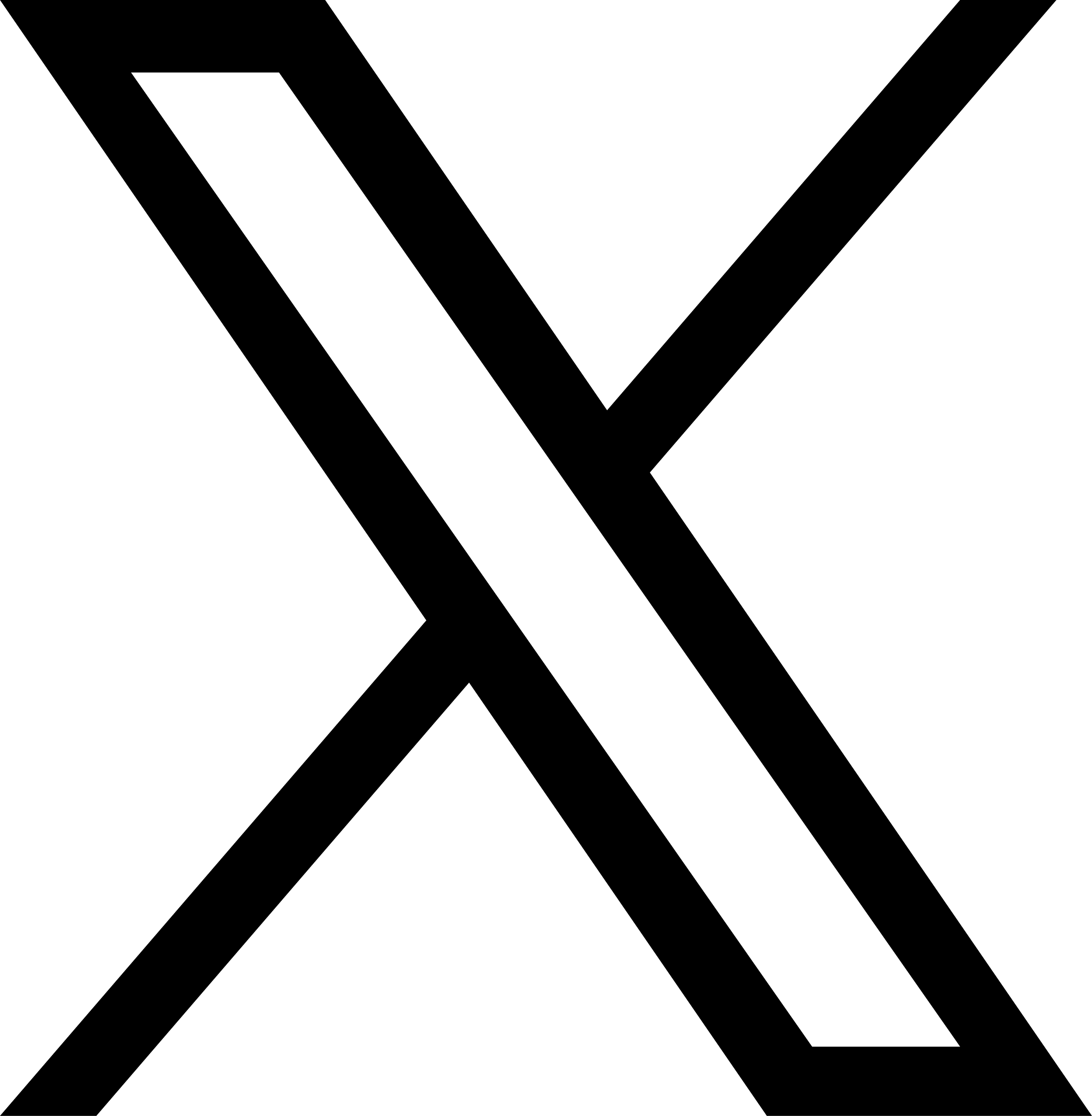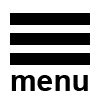母校関係者の偉業-食生活編-PART1
斉田育秀(21製大)
時代の流れで忘却の彼方に埋もれつつある話題を提供したい。身近な「食」に関わる母校関係者の偉大な功績の話である。少々長くなるので2回に分けて紹介したい。
1.「ミカン缶詰」を発明した“荒川驍”
現在のスタイルのミカン缶詰を最初に製造したのは広島・大長の加島正人という人物で、昭和3年の話である。ミカン缶詰はミカンの小袋(じょうのう)が剥離され、見た目も美しく食べやすく実に美味しい。この小袋を剥離する基本的技術「アルカリ剥離法」を考案したのは、大阪工業試験所の技師・荒川驍(17水講)で、大正の終わり頃の話である。それまでにもミカン缶詰の試作は色々と行われたようで、スペイン式(小袋付き)ミカン缶詰などが研究されたが、物がモノだけに“ミカンせい(未完成)”であった。「アルカリ剥離法」を知った加島は独自の研究に入るのだが、それを援助したのが同郷の廿日出国三郎・要之進(現アヲハタ創業者:26水講)親子である。完成したサンプルは要之進を通じキユーピー創業者の中島董一郎(10水講)に届けられた。早速中島はイギリス・アメリカ等へサンプルを送付し、これが翌年実を結び後に日本の重要な輸出品になるのである。ミカン缶詰は昭和13年には194万函製造され、輸出は121万函(内80%がイギリス)になった。荒川のアイデアは缶詰の歴史に燦然と輝く発明となったのである。
2.日本で最初の本格的「まぐろ油漬缶詰」を製造し企業化へと導いた“村上芳雄”
1903年アメリカ・カリフォルニアのA・Pハーフヒルが創作したまぐろ油漬缶詰は、「chicken of the sea」と呼ばれアメリカでは重宝がられていた。日本でも明治年間から各地の水産試験場で研究試作が行われていたが、国産初の本格的なまぐろ油漬缶詰の試作製造に成功したのは、静岡県水産試験場の技師・村上芳雄(24水講)である。彼は昭和2年に全国会議の席上で農林省技師・江副元三(14水講)が発言した、「まぐろ油漬缶詰の対米輸出は有望」という話に触発され、独自の研究を始めた。昭和3年に試作品を東洋製罐の高碕達之助(9水講)に見せたところ、「輸出可能」の折り紙を付けられた。そこで水試場長の後藤節蔵(12水講)の英断による予算の裏付けのもと、昭和4年5月に焼津水産学校で試売品として100函(4,800缶)を、教諭の吉川吉男・堀田美桜男(25水講)や生徒の協力を得て製造。「富士丸ブランド」でアメリカに送ったところ、即完売したとのこと。実は前年に広島の新見缶詰所がトライしているが悪臭・舌を刺すなどで通関出来なかった。また村上の凄さはこの缶詰の企業化を実現したことである。「静岡県はミカンの産地なので、夏場はビンナガでまぐろ油漬缶詰を、冬場はミカン缶詰を作れば工場が年間操業出来る」と説いた。これに当時清水の有力者であった鈴与商店(現鈴与)の鈴木与平が応え、昭和4年12月に「清水食品」が設立され、翌昭和5年の夏場から本格的に企業ベースでの製造が開始された。昭和6年には後藤缶詰所(現はごろもフーズ)が設立され、以後同業者が続々と続くことになる。まぐろ油漬缶詰を巡っては実に多くの母校出身者が関係しながら世に送り出した商品だったと言える。尚まぐろ油漬缶詰の「青肉」問題に、トリメチルアミンが重要な役割を果たすことを指摘したのは、東水大教授・学長の小泉千秋(5製大)であり、この缶詰との縁はその後も続くことになる。
3.「魚肉ハム」を考案した水産練り製品の世界的権威“清水亘”
今日のように畜肉が潤沢に供給されなかった大正の初め、魚肉を原料にハムやソーセージを作る試みが全国の水産試験所で始まっていた。昭和10年頃当時水産講習所の教授であった清水亘(27水講:後京都大学名誉教授)は、まぐろ肉をプレスハム風に、本格的な「魚肉ハム(ツナハム)」を考案した。清水の指導で昭和13年には南興食品が製造を開始、東京のデパートで好評を得た。その後昭和24年西南開発工業協同組合(現西南開発)が魚肉ソーセージの試作に成功し、昭和26年「スモーク・ミート」(鯵主体)として発売。昭和27年には日水がツナ主体のツナソーセージを発売し、大洋・日魯など水産各社が続くことになる。因みに昭和12年頃に日魯で鱒肉70%、豚肉30%のソーセージを開発し発売しているが、これを魚肉ソーセージと呼ぶには畜肉が多過ぎる気がする。いずれにしてもこの分野の嚆矢は清水の発明にある。
4.画期的解凍法により「鯨肉」を身近で美味しい食べ物に変貌させた“田中和夫”
日本は昭和63年に商業捕鯨から撤退したが、鯨肉は東京オリンピック直前の昭和38年まで、肉類の中で最も多く消費されていた。一人一日当たりの供給量(農水省:食糧需給表)で見ると、昭和38年は鯨肉:5.6g 豚肉:5.4g 牛肉:4.1g 鶏肉:3.9gの順である。鯨肉は戦前より独特の異臭や店頭で大量のドリップ(肉汁)が出るので人気は芳しくなかったが、戦後食糧事情の観点から急速に研究が進んだ。一般に動物が死ぬと肉は死後硬直を起こすが、硬直にはエネルギーのもとであるATP(アデノシン三燐酸)が関与する。経時変化で三燐酸はニ燐酸・一燐酸と変化し肉には旨味が出てくるのだが、その先には腐敗が待っている。冷凍鯨肉を解凍すると極低温で残っていたATPの作用で、急速に硬直が起き、肉が収縮してドリップが大量に出ることが分かった。そこで 東水大教授の田中和夫(44水講)が、鮮度を落とさずATPを消費させる方法を考え「出来るだけ鮮度の良い鯨肉を凍結し、出来るだけ低温に冷凍保管し、販売直前に-2℃の室で5日間保管し、その後通常の方法で融解すればよい」と提唱した。これにより美味しい鯨肉が食べられるようになった訳である。 (映画史・食文化研究家)