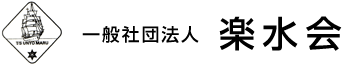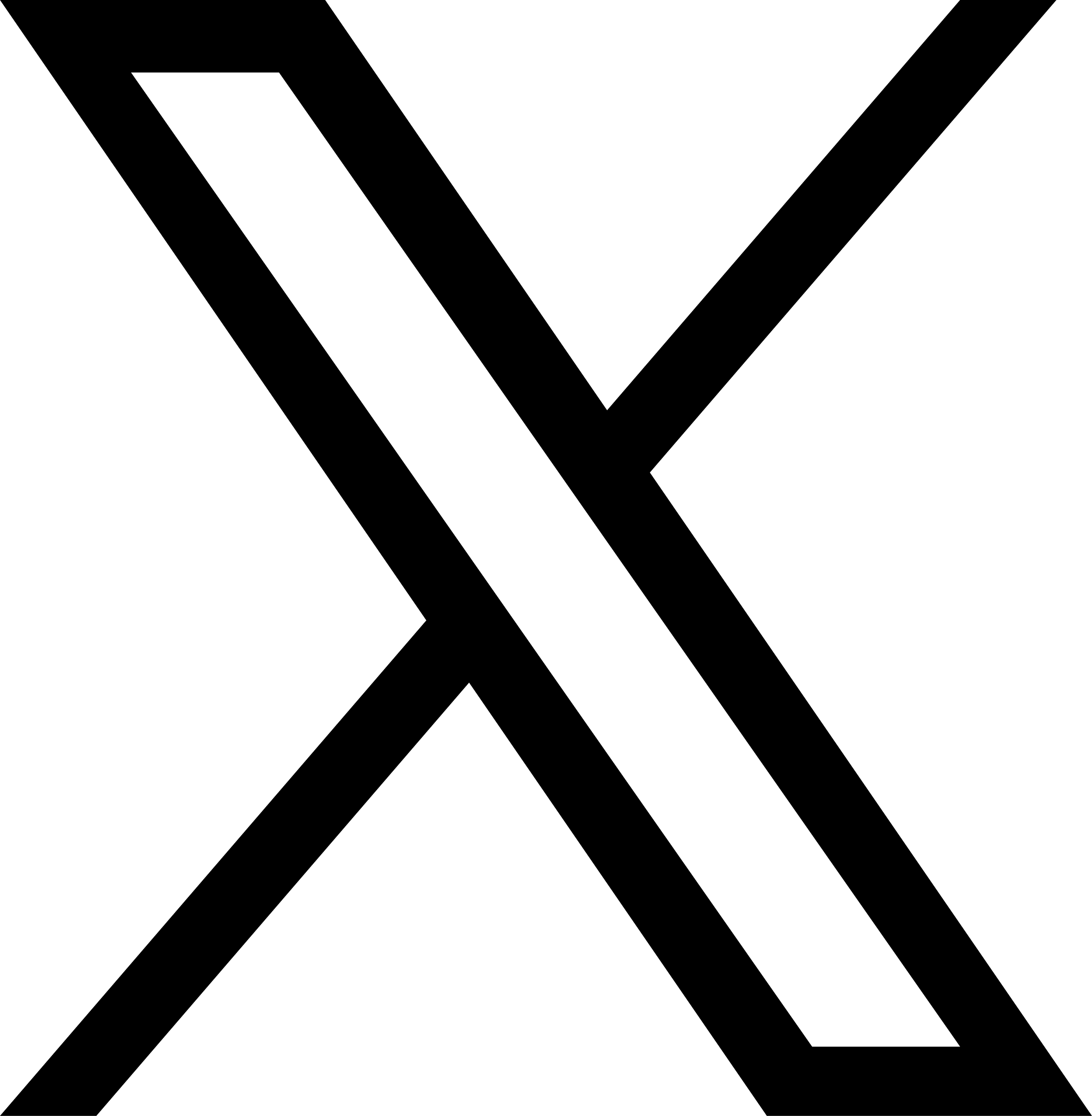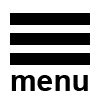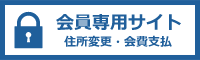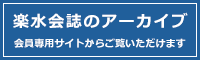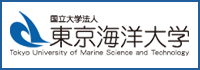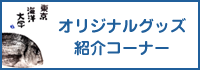栃木県那須郡那珂川町・馬頭高等学校からの便り
青木 信太郎(41海洋)
海のない栃木県東部、那珂川の支流である武茂川沿いに馬頭高等学校はあります。普通科1クラス(40名)、水産科1クラス(25名)の小さな学校で、公共の交通機関に恵まれない立地ながらも、水産科の研究において「ウナギの種苗生産」「休耕田を利用したホンモロコ養殖」「キャビアの生産」や、普通科の地域探求授業は、地元では注目される学校です。今回、本校水産科の取り組みを紹介させていただきます。

1 馬頭高校について
馬頭高校は、昭和21年に馬頭農学校として創立されました。その後、普通科、家政科が設置され、昭和47年に水産科は設置されました。設置当時は、休耕田を利用したコイの養殖や、実習場を作るために水産土木の授業もカリキュラムに含まれていたようです。現在は、「淡水魚の養殖」「食品製造」「河川環境」を教育内容の3本柱としています。
実習場は、校舎から4キロ離れたところあります。食品加工施設、養殖池、実験室があり、水源は農業用水から引く河川水と伏流水をくみ上げる井戸水の2系統あります。養殖をしている主な魚は「アユ」「ウグイ」「キンギョ」「チョウザメ(ベステル)」です。研究対象魚として「ウナギ」「イシガイ」「ミヤコタナゴ」(環境省届済み)や、その時々で様々な生物を飼育しています。
2 「課題研究」について
本校は、栃木県から平成5年度に科目「課題研究」の研究指定校に任命されました。課題研究では生徒自ら研究テーマを設定し、探究活動を行っていきます。本校では、研究収録として年度末に記録を残しています。生徒の考える様々な研究は、多くの皆様の協力をいただき実施されています。課題研究の成果として、いくつか紹介していきたいと思います。
(1)ウナギの種苗生産
ウナギの完全種苗生産は、現在では可能なものとなっていますが、本校では私が赴任する前(平成18年以前)から生徒の研究テーマとなっていました。この研究においては、水産技術研究所(南勢庁舎)のご指導の下、地元の簗漁から親魚の購入、ゴナトロピン等のホルモン剤投与の試行錯誤を経て、全国の水産高校では初めてふ化に成功しました。現在は、地元の川魚店と連携しながらダクチロ駆除等の健全な養殖を実現していくための研究を行っています。
(2)キャビアの生産
この課題は、キャビアを食べたことのない生徒が設定した研究テーマです。こちらも10年以上かけて成功しました。種苗は㈱フジキンからベステル種を入手し飼育していましたが、成熟がうまくいかない状態でした。栃木県水産試験場に協力を経て栄養不足であることと見逃しがあったことが判明し、東日本ホテルの総料理長のご指導のもと、全国の水産高校では初のキャビア生産ができました。

(3)河川環境改善
この課題は、近年の河川環境悪化を危惧する釣り好きの生徒が始めたテーマです。こちらは国土交通省、栃木県水産試験場の力を借りて河川に巨石を設置したり、河川工事をする際の提言をしたりする程の評価を得て、近年は全国の生徒研究発表会でも高評価を得るまでの成果を上げています。
(4)実習製品
1)魚醤
秋になると遡上し、産卵後に死んだサケの死体で覆われていた武茂川を見た生徒が何か利用できないかということから魚醤づくりはスタートしました。宇都宮白楊高校の酵母に詳しい先生から指導を受け、耐塩性酵母を分けていただき、3ヶ月で生産可能なサケ魚醤ができました。栃木県からは特別採捕許可をいただき、採卵後の身を利用したもので地元の道の駅でアユ魚醤と共に販売しています。

2)ピラルクーのグリーンカレー缶詰
地元の水族館なかがわ水遊園からピラルクーの養殖についてお誘いを受け、ピラルクーの成長について研究を始めたときに㈱ライデンシャフトがペルーから輸入しているフィレを利用し、なかがわ水遊園で販売しました。好評でしたが輸入が途絶え、現在はパンガシウス(ナマズ)で製作しています。ピラルクーは10cm、15gから1年で1m、10㎏を目指せる成長の速さと白身で日本人好みな淡白な魚なので、廃熱利用が可能な大規模な養殖池があれば日本国内でも需要はあるのではないかと思います。本校では、光熱費が賄えず飼育を断念しました。

3)アユのオイル煮缶詰
これは、地元川魚店から譲り受けた規格外のアユを利用して製作したものです。焼いて燻製下身を調味し、オリーブオイルでつけたものになります。生産量が少ないので、学校祭や地元の催事で販売しています。

アユのオイル煮
(5)その他
その他として、「ニホンナマズ」の養殖を埼玉県水産試験場と研究を行い実現し、この研究がきっかけで秋篠宮殿下に御来校していただきました(平成10年)。「ホンモロコ養殖」は、現在地元の方々8団体が耕田を利用して養殖を行っています。栃木県の郷土料理「しもつかれ」を缶詰にしたものは、文化庁の「100年フード」認定にも貢献できました。
3 小説「ナカスイ」について
著者の村崎なぎこさんは、「ナカスイ」の前作「百年厨房」で「日本おいしい小説大賞」を受賞した作家の方です。栃木県地元新聞に上記の課題研究成果や各催しに参加した際の記事をみて本校に興味を持っていただき、小説の題材としていただきました。今年7月には、NHKラジオドラマ化も決定しています。執筆にあたっては馬頭高校卒、海洋生物資源学科4年、生井美沙季さんも監修にあたっています。水産高校の女子生徒が頑張る姿を描写した作品です。高校3年間で3巻完結となっていますが、かつて清水海上技術短期大学にあった司厨科をイメージした学校に進学し、将来を目指す形で完結しています。司厨科の様子や司厨員についての情報をいただければ、4巻も書いていただけるかもしれません。情報をお持ちの方は、ぜひともご提供をお願いいたします。

小説『ナカスイ!海なし県の水産高校』
4 おわりに
馬頭高等学校水産科は淡水魚をメインに学ぶという特異性を活かして、今後も内水面養殖に貢献できるような研究や学習の実施、水産業後継者育成をしていきます。県内外問わず皆様のご協力あってのことなので、今後も小さな学校ではありますが、よろしくご指導・ご支援のほどをお願いいたします。
最後に、水産高校への就職の道をつないでくださった竹内正一先生(7漁大)に本当に感謝いたします。
栃木県立馬頭高等学校 教頭(現所属:栃木県立小山北桜高等学校 第一教頭)