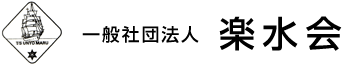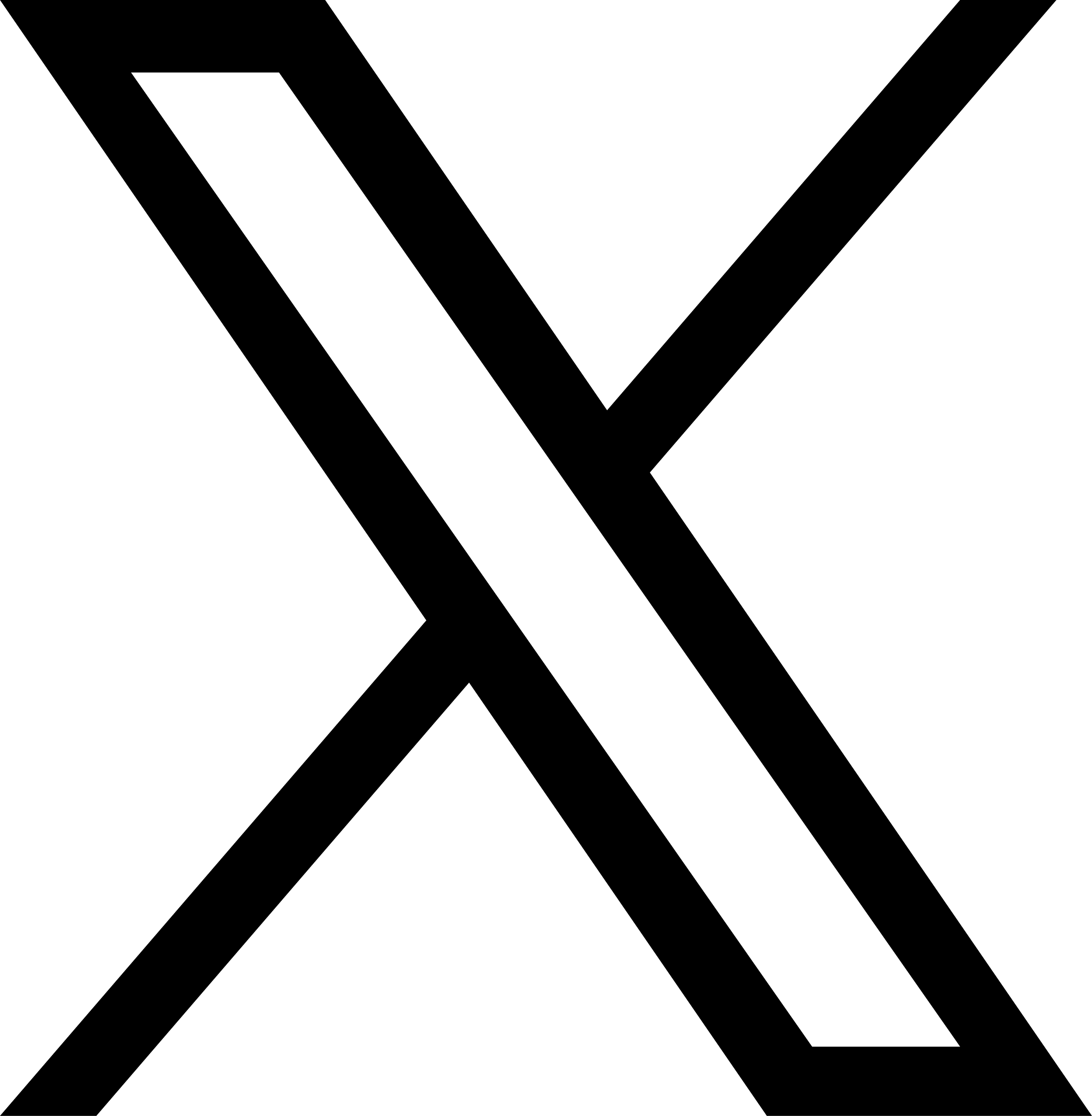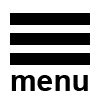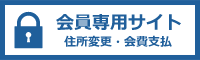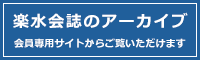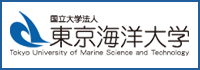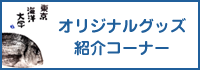東京海洋大学 入学から現在に至るまでの軌跡 ~悔いの残らない4年間を~
松崎 愛海(18海資源)
1.東京海洋大学に入学した経緯
本学を目指したきっかけをくれたのは、母である。まず、幼い頃から水族館に連れて行ってもらうことが多く、特に鯨類が好きだった。イルカショーやシャチショーなどは欠かさず見る習慣があったため、そこから鯨類への興味は始まった。進学先を決める高校時代、実は最初から本学を志望していたわけではない。心理学や経済学にも興味があり、文系に進むことを考えてみたこともあった。それでも高校2年生の夏頃には薬学部か本学かの2択に絞った。薬学部は、両親が薬剤師であるためやりがいのある仕事という印象があったこと、国家資格が必要な職業であり、将来が確約されていることが魅力だった。それに対して、本学は自分の好きなことを学ぶことができるという大きな利点はあるが、将来は確約されていないことが懸念点であった。しかしながら、その後2回本学を実際に訪問して、やはり大学では自分の好きなことをしたいという気持ちが強くなったことが決め手となり、本学を目指すことに決めた。
一度決めたら全力で努力する性格であるため、コロナ禍でも自宅学習を怠らなかった。さらに少しでも合格する確率を上げたいと考え、迷ったうえで公募推薦入試と一般入試を併用する形で受験した。公募推薦入試は不合格だったものの、志望理由書を書く過程で自分が本当にやりたいことや、本学に入る理由が言語化されて明確になり、その後の大学生活の計画を立てる際に非常に助けになったため、推薦入試を受験したことを無駄だと思ったことはなく、後悔も一つもしていない。
また、私は最初から鯨類学研究室に入ることを希望していた。そのため、志望理由書には、クジラのソングと人為雑音の関係と、その改善がしたいという目標を記述した。この目標は、高校2年生のときの経験から生まれた。高校では硬式庭球部に所属し、高校2年生の1年弱にわたって部長を務めていたのだが、人間関係や部の運営の面で非常に悩んでいた時期があった。そんなとき、インスタグラムで偶然ザトウクジラのソングを聞き、その音に魅了された。そこからソングについて調べていくと、人工物によって生じる海中の音(人為雑音)がソング自体や個体同士のコミュニケーションに影響を及ぼす可能性があるということを知り、この美しい音を守りたいと考えたのが鯨類学研究室を目指したきっかけである。
2.大学生活
大学生活は、とにかく努力することを意識した4年間であった。私はこの4年間を通し、継続は力なりということを実感した。
入学後1年間はまず授業とTOEICに力を入れた。大学の授業に関しては、もともと理数系の科目が得意ではないので努力でカバーしようと考え、不明な点は授業担当の先生に積極的に質問した。特に物理に関しては基礎しか履修していなかったため、高校物理の参考書を購入して一通り取り組み、ある程度理解してから大学の講義を受講した。TOEICに関しては、まず入学前の試験に向けて勉強し、790点を取ることができた。さらに、入学前から大学のプログラムである海外探検隊に興味があったため、より英語力を強化したいと考えていた。そこで、グローバルコモンのカウンセリングに大学1年生の1年間、週に1回のペースで通い、ほぼ毎日学習を続けていった結果、2022年1月のTOEIC学内実施試験では、850点を取ることができた。その後は、海外留学を見据えてIELTSに教材を変更し、継続して勉強を続けている。受験費用が高価なためなかなか受験できていないが、今年中には試験を受ける予定である。
当初の予定では、大学1年生で海外探検隊、大学2年生あるいは3年生で短期留学に挑戦する計画であった。新型コロナウイルスの影響で計画通りとはいかなかったが、大学2年生の夏には目標通り海外探検隊でシンガポールに、大学3年生の夏にはJICA海外協力隊でセントルシアにそれぞれ1カ月間ずつ滞在した。海外探検隊はプログラムに沿って様々な機関や大学で仕事や研究に参加する方式、JICA海外協力隊は自分たちでプログラムやスケジュールを決定する方式と、それぞれ異なる経験であったが、どちらも非常に有益であった。JICA海外協力隊では学部で環境に関して学んできたことを活かし、マイクロプラスチックについての啓発ポスターを作成した(写真1)。どちらの経験にも共通することは英語を話すことが怖くなくなったことである。必ずしもスピーキングが上手になった(発音が上手になった)わけではないが、とりあえず話してみるという目標のもと過ごしたことで、自信がつき、英語が分からないからといって黙ってしまうことはなくなった。その結果、会話がスムーズに進むようになり、自信がついたとともに、様々な人と出会い、意外な地域性に触れ、人の温かさを感じた。これらの経験を通し、より社交的な性格になったように感じている。

学業に関しては学部4年間にわたって自分を律し、最大の努力をすることができたと自負している。結果として、大学4年時には「学部4年間で最も高い成績を修めた学生」として令和6年度3月期学生表彰を受け、総代としても選出された(写真2)。

3.鯨類学研究室に入るまでの経緯
現在、私は本学の鯨類学研究室に所属しているが、配属までに紆余曲折があった。そのため、今所属できていることは奇跡であると私は考えている。
鯨類学研究室は入学前から志望していたため、行動は早い方がいいと考えて、大学1年生の7月に研究室を訪問した。ただし、この時点では音響研究の実績がなく、本研究室では指導できないと断られた。その後、大学3年の7月にやはり本学の鯨類学研究室で研究がしたいと考え、再度研究室訪問伺いのメールを送った際、八丈島のザトウクジラのソングデータがあることを伝えられた。現在の担当教員である村瀬弘人准教授が、私が研究室訪問をしてから、2年の秋から春、3年の秋から春の2シーズンにわたって録音を実施してくれていたのである。音響研究はできないと諦めていたため、非常に驚いたと同時に嬉しかったことを覚えている。
大学1年時の訪問の際、鯨類学だけではなく、満遍なく勉学に励むようにというアドバイスを受けた。その言葉を信じ、鯨類学研究室に入りたいという一心で勉学に励んだ。その私をみた担当教員が期待に応えてあげたいと思ってくださり、現在自分がずっと携わりたかったクジラのソングの研究ができている。これらの経験から、私は、「何事も行動力が大事で、やりたいことが決まっているなら、その思いは伝えることが大事である」、「努力は裏切らない」の2点を実感した。
4.鯨類学研究室での1年間
大学4年生の、鯨類学研究室における1年間は、長いようで短く、さまざまな経験を積んだ1年間であった。
はじめの1~2カ月は知識をつけることに力をいれ、ソングに関する論文を読み漁った。その後、6月頃からデータ解析を開始した。音響解析は自分のやりたかったことであり、ザトウクジラのソングは大好きな音であるから幸せな時間ではあったが、非常に時間のかかる、骨の折れる作業であった。夏季には7月後半~9月前半までの長期航海(鯨類目視調査)に参加した。①将来を見据え、長期航海に慣れておきたい。②さまざまな鯨類をこの目でみたいという2つの理由から挑戦したいと考えた。船酔いがひどいため、大学4年間の中で最もつらく苦しい夏であったと断言できるが、それでも海に囲まれた生活という非日常の中、日常では体験できないことの連続で、毎日が充実していた。やはり目でみた鯨類は圧巻で、自分が愛してやまない鯨類は「本当に海に実在するのだ」と感動し、涙したことを覚えている。その後、10月以降は学位論文の執筆に集中し、3月に日本水産学会において口頭発表を行い、1年間の成果を示した。学会での発表は初めてであったが、自分が1年間取り組んできたことを、自信を持って示すことができたと考えている。
5.将来の目標
まだ検討中ではあるが、研究者を目指す、あるいは海に関する仕事に就くことを考えている。研究者を目指すなら、博士後期課程に進学し、その後ポスドクとして海外留学したいと考えている。これは、私の担当教員の影響が大きい。村瀬准教授は海外の大学院に進学し、さまざまな研究機関に就職した後、現在の教育職に就いている。学生に親身に寄り添ってくださる先生である反面、研究の場では鋭いコメントで議論される実力もある方だ。私は、研究者を目指すなら村瀬准教授のような研究者になりたいと考えている。そのため、海外経験を積んで、コネクションを作り、世界で通用する研究者を目指すことが目標である。ただ、現在就職活動も始めている。就職するならば何らかの形で海に関する仕事に就くことが目標である。薬剤師であり薬局を営んでいた祖父が、生前、本学に入学した私に「本当は船乗りになりたかったが、金銭的な理由からなることができなかった」と話してくれたことが心に残っており、アカデミックに残るにしても、就職するにしても、海には関わっていたいと考えている。
これから本学を目指す方、希望する研究室がある方に向けて伝えたいことは、自分の座右の銘でもある「やらない後悔よりやる後悔」だ。何度も迷う場面はあったが、どの選択も挑戦しないで保守的になるよりも、とりあえず挑戦してみて、それから考えることを意識したところ、自分にとって悔いのない大学生活を送ることができた。この選択をしたら対価として犠牲になるものがあるかもしれないと思う気持ちも理解できるが、その選択の先に自分がやりたいことや、なりたい姿があるならば、行動してほしいと考える。
大学院海洋科学技術研究科 海洋資源環境学専攻 大学院博士前期課程1年